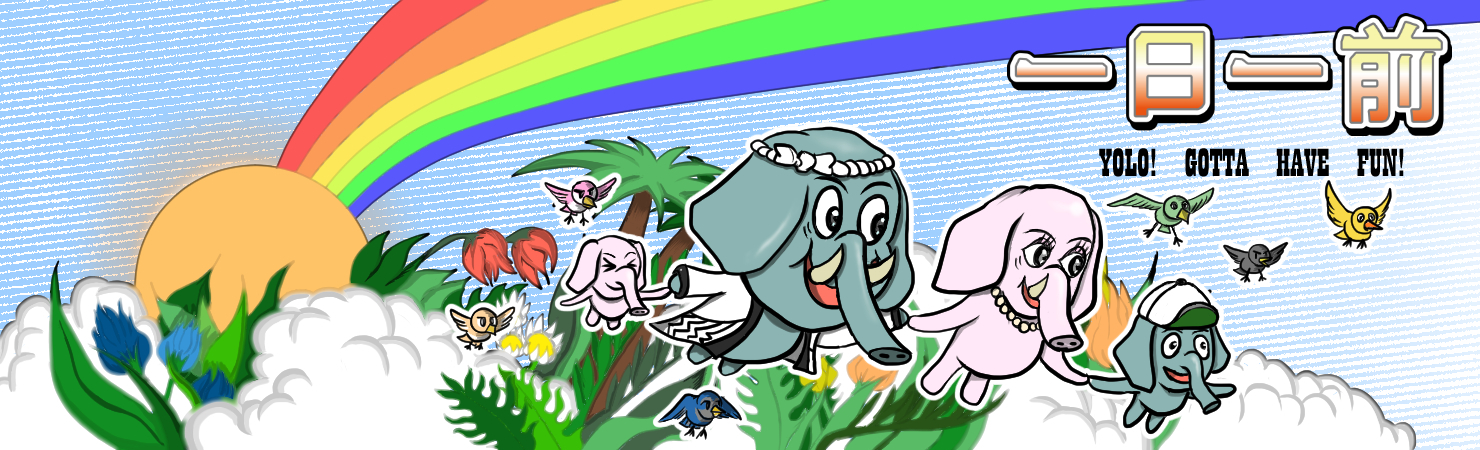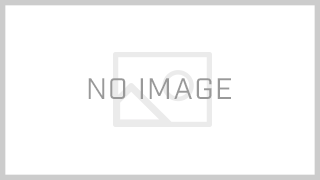2018年あけました。おめでとうございます。まるぞうです。皆様、本年もよろしくお願いします。今日は、朝、6時30分起きで、バタバタとした正月を過ごしております。明日は、奥様の実家にて、親戚の集まりに参加し、お泊まりの予定です。もう、日が変わり、1月2日になってます。考えれば、後、休みは、1日ですね。4日から仕事なので…
毎年のことですが、年末年始は、忙しので、1日か、2日ぐらいゆっくりした休日が欲しいと思う。
年賀状
話は、変わりますが、皆さんは、年賀状のやりとりをしてますか。インターネット、SNS、Line、メールなどで済ましてますか?いっときは、僕もそういう時がありましたが。結婚して改めて思ったのですが、やっぱり、年賀状は、いいですね。いつも、年賀状を作成しているときは、業者に出そうか、自分で作ろうか悩み、いつも年賀状の作成日が、年末ギリギリになるので、結局、自分で作りますね。最近は、業者に出されている友人の年賀状も多く見受けれますが。年賀状の歴史を紐解くだけでも面白いものですね。
年賀状の起源
人類社会には、古代から古代から年賀の習慣があったんだって。世界の四大文明には、新年を祝う宗教的儀式の痕跡が数多く残されてるみたい。宗教の関係で、東南アジアには、新年を祝う年賀の書状が交わされたんだって。
日本に、百済から中国式の暦が伝わったのが6世紀の半ばぐらい。7世紀の後半ぐらいに郵便制度の原型が出来て、誰が始めたかは不明みたいやけど、貴族階級には、年賀の書状が広まったみたい。そこから江戸時代になると、飛脚便って文化が発達して武士階級だけがではなく、庶民も手紙を出すよになってきたんだって。江戸時代の後半には、日本は世界一の就学率で識学な国だって言われてるんだって。やっぱり日本は凄いね。寺ごやで読本や習字の手本として使われていたのが、主には手紙とかだって。昔で言う「よみ・かき・そろばん」の「よみ」と「かき」は、手紙の読み方、書き方を寺小屋で習ってたんだって。
前島 密
明治維新には、欧米をモデルとして、前島密が、通信制度の改革をしたんだって。1870年(明治3)に郵便事業の創業をしながら、世界を回り、世界の郵便事業を学び、その経験を日本の郵便の制度に活用してんだって。最初は、東京と京都と大阪だけだったんだけど、72年には、全国に一律料金で、郵便物が届くようになったんだって。その発展に伴って、郵便局と郵便ポストが全国のいろんなとこにできたんだって。1885年(明治18)には、日本国民の間に郵便が定着したみたいだよ。ハガキは、イギリスのポストカードをモデルにして、1873年(明治6)年に誕生したんだって。前島密ってスゴイよね。
その後の年賀状の歴史
前島密が郵便の制度を整えてからは、年賀状が出来るまでは、一瞬だって。もともと上流階級の人が、手紙として封書で年賀状を送っていたのが、ハガキスタイルに変え割ったことによって、庶民にも年賀状が、定着したんだって。その後、戦争の間は、年賀状を控えましょうって、呼びかけもあったみたいですが、第二次世界大戦後は、お互いの安否確認や、生存を喜ぶ物として年賀状が、活用されたんだって。その後に、年賀状にお年玉当選番号を付けたりと現在の形になったいくんでって。1997年(平成9)の37億通をピークに微減傾向にあるんだって。
今後の年賀状って
今回、年賀状の起源をめっちゃ簡単にまとめましたが、インターネットに押されて、衰退していくのか全く読めない。年賀状を作成する手間は、ありますが、もらった時は、嬉しいものですね。年賀状を見ながら年賀状の差出人の方の話題になり、家族での会話にもなる。戦後の安否確認ではないが、お互いの現状がわかる。やっぱり、年賀状は、いい。
前に「探偵ナイトスクープ」で、一度会った人に、年賀状を出すって人がいた。年賀状を出すのが趣味とのことで、1200枚ぐらい出せれていたかと思う。凄い。
2018年、始まりました。気持ち新たに心機一転、共に楽しい日々を送って行きましょう。今年も、まるぞうブログ『一日一前』をよろしくお願いします。
年賀状の起源がきになる方は、サイトも見て見てください。http://nengahaku.jp/history.html