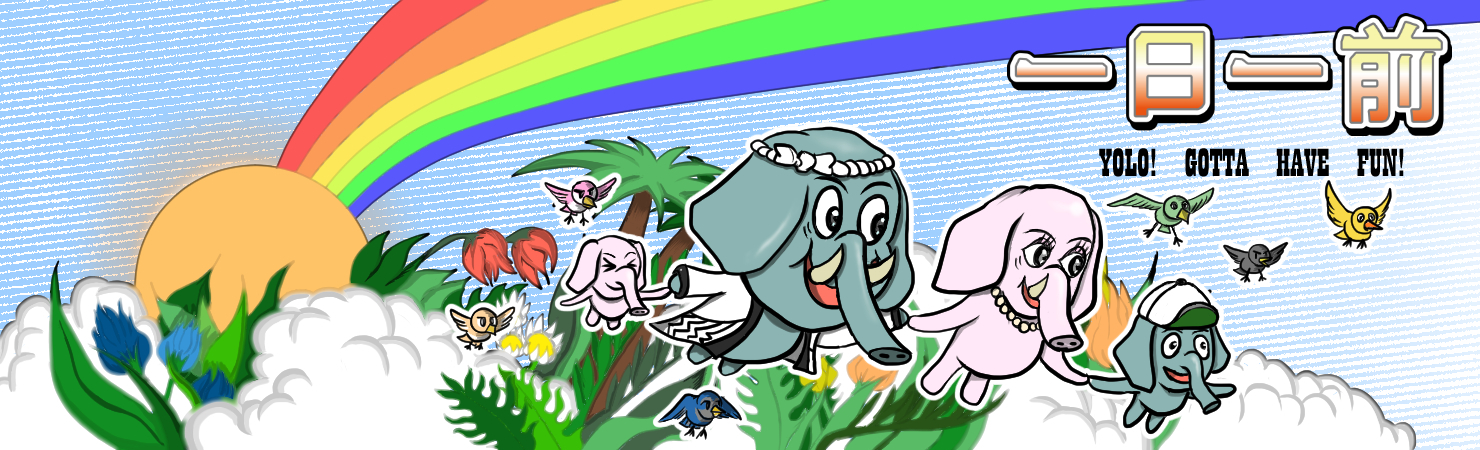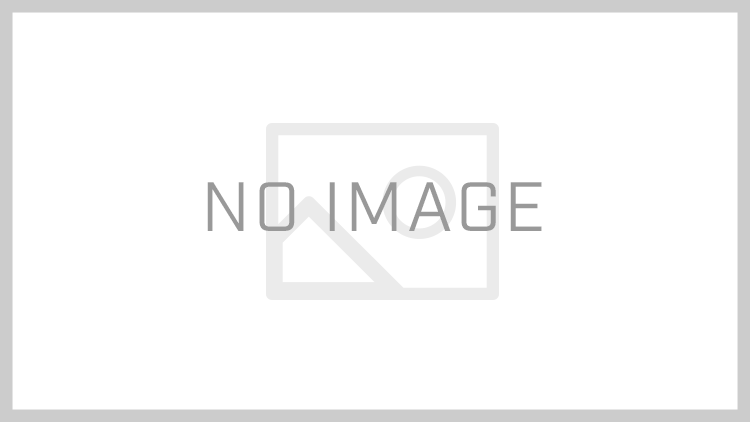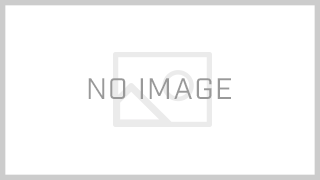どうも、まるぞうです。来週までは、週末が休みなので、家族でのコミュニケーションが取れるので、充実した日が送れている。本当に家族でのコミュニケーションの大切さを痛感している今日、この頃。今日は、今朝にアップしたブログの続きを書いて生きたいと思う。
仕事選び
前回のブログで、僕は、鉄工所(鍛冶屋)からの転職をしなくてはいけない状況になった。それは、低賃金で、社会保険などがなかったこと、また、結婚したこともあり、生活費もきつかった為に、週末の休みは、バイトをしていた。そんな生活を、結婚してからの1年半ぐらいした。休みという休みは、ほとんどなかった。今、考えれば、良くやっていたなと思う。そんな生活にケリをつけようと転職活動をしながら仕事をしていたけど、うまく次の仕事には、スライド出来ずに、退職をした。それからの2ヶ月ぐらいは、知り合いのつてで、以前に勤めていた仕事の手伝いをバイトとして行っていた。正直、毎日良く仕事があって、生活ができているなと感じた。そんな日々を過していた時に現在の職場で、製造業をして見ないかと誘いを受けた。定職についていない僕は、安易に現在の職に飛びついてしまった。
勧誘の経緯
なぜ、僕が、現在の製造業に誘われたのかと言うと、僕は、前職の鉄工所で働いている時に、今の職場で協力会社として入ってる会社からの仕事で、設備メンテナンスや、設備の改善などで度々訪れていた。たまたま、誘ってくださった方と仕事をする機会があり、その時の仕事の頑張りを認めてもらい、現在の職場が、人を探したいるタイミングでもあったので、誘っていただいた。
現在の職場へ
僕は、一流企業の子会社で、契約社員として製造業を行うこととなった。2011年7月のことだった。前職より給料は、上がり、社会保険もあったので、金銭面では、かなりアップした。しかし、仕事はと言うと初めての交代勤務で、製造部門が4つある職場の中でも仕事内容が厳しく、人の出入りも多かった。僕が入った年にも、あと4人ほど入ったが、みんな辞めた。今までで、カウントすると30人ぐらいは、やめていると思う。新入社員も含めてだ。
消えて行く労働者
なぜ、新たに入ってくる労働者が辞めていくのかを僕なりに考えて見た。
1.しっかりとした教育ができない。
まず、一つめの課題のしっかりした教育ができないのは、なぜか。教え方に問題があるのか。今の教え方は、現場で作業を、社員や委託社員などが、新人とペアになって教える。手順などは、人によって様々だ。作業標準書はあるが、現場で教えることが先行していて、従業員でもなかなか作業標準書を開くことが少ない。また、日勤などの勤務で、ゆっくり教える事が出来なく、交代勤務になってから教える為、交代勤務者に時間の余裕がなく、教える事が出来ない。今、現在は、日勤では、作業を教える事なく、日勤時に雑用をさせる為、作業を教えない。交代勤務者は、製造工程が、詰まっている為、工程を回すのに精一杯で、教える事が出来ない。現状を見て、改善するなら教育者を決め、作業標準書を元に作業を教育し、一つの作業を覚えさせるのに時間をかける。
2.一人にかかる仕事量が多い。
交代作業者の労働内容を見てみると、まずは、稼働ラインのスタートとストップ。稼動時の稼働管理。稼動時の発生スクラップの集計とそれに伴う、スクラップ削減の対策を考え、設備の改善や、改造。スクラップ削減対策などの資料をまとめて、毎月の会議。製造工程時のサイズ替え作業。製造工場の改善や、不要物の撤去など。新人の教育。半年の改善活動の発表会の発表と資料作成。自主保全と題し、毎日、現場のエアーや蒸気や、使用工具や測定治具や備品などの管理をし、チェック用紙に記入など、製造をおこながらのデスクワークや、現場改善と仕事量が多い。日勤班が、サイズ替え作業、デスクワークの部分などを取るなどしてくれると、作業が減る。日勤班は、シニア社員と社員を合わせて6名。共に仕事を選び行う為、面倒な仕事や、やりたくない仕事は、交代班に回ってくる。仕事の仕方もそうだが、全体的に人員不足である。仕事を細分化して分業化すれば、それだけで、必要な人数や欲しいスキルもわかる。また、シニアや主婦なども雇えるようになるのではないかと思う。
3.製造する中で、人力での作業が多い。
設備が古い為、改造することもできなく全部、人の手で行わなくてはいけない。また、今まで自動だった部分も、設備の老朽化から人力で行なっている現状だ。設備が故障しても、その時々で改善した内容が、履歴として残っていない為、どこをどう触っているのかわからず、原因が掴みにくかったり、わからない事が多い。このことから来年に、新しい設備や、現状の設備を移設して新しい建屋での製造が、開始されるが、現在、新しい設備のライン設計などを製造をやった事がないものが、作っている為に新しい設備を稼働したら問題が出て、こんな設備で製造ができなとなるのは、見えている。交代作業者の負担が見えている。このことから、また、新しい問題提起が出てきた。
決定権
3つの問題に対し、解決をするならどう言った事が、必要となるか。それは、上長の決定権である。良き判断をし、決定する。その事が出来なければ、末端の交代作業者に仕事が集中し、離職者が増える。なぜ、現場に合わせた判断をし、決定ができないかだ。それは、子会社の課長以上の役職を親会社の人間が、行なっている。そのことから、現場で製造をした事がないので、製造にかかる工数を知らない。なので、作業を軽視し、工数を減らす。また、交代人員の欠員も簡単に考え、他部所とのいじの張り合いで、この人員でこの工程は、こなせないと判断し、勤務の変更や、工程の変更ができない。
結果
今回の問題提起での答えは、親会社と子会社を全くの別物として、人員の配置を考える。そうすることによって、以上の3つの問題も解決してくる。また、子会社として、親会社の人員を役職をつけて配置する際は、コンサルタントなどを入れて、経営方針を考えていく事が望ましいのではないかと思う。
今回、色々と考えて見たが、経営の部分は、関われないので、このことを踏まえての転職をするべきかと思っている。まだ方法があればいいが、提案があったら、教えてください。よろしくお願いします。
今日も最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。明日は、夕方から待ちに待った、バスケをしにいくので、楽しみ。現在、筋肉痛なので、無理のない程度に頑張ります。