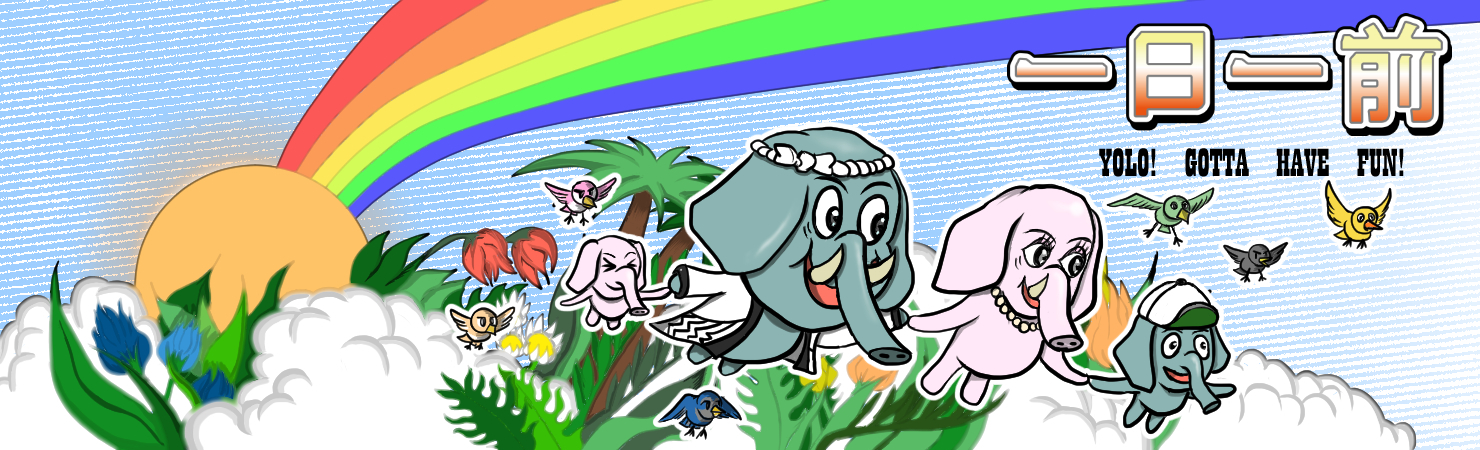前回の投稿から間が空いてしまいました。個人的な事情で、ブログの更新をできなかったのですが、その日に終わらない用事がいっぱいで、その中には、親族の結婚式などがあり、本当に久しぶりのバタバタとした日々を過ごしていました。
皆さんは、楽しい日々を過ごしていますか?夏に向け、徐々に気温も上がってきていますね。夏が待ち遠しいです。
さて、前回の続きになりますが、変わりゆくものづくりの製造現場について書いていきたいと思います。前回のブログを読んでない方は、こちら。
自動化される製造ライン
 人員を確保できない現場は、どのような対策を取るようになったんでしょうか?多分、多くの方は、予想されていると思いますが、そう、自動化です。製造ラインを自動化にすることにより、少人数での生産活動に切り替えていくのです。
人員を確保できない現場は、どのような対策を取るようになったんでしょうか?多分、多くの方は、予想されていると思いますが、そう、自動化です。製造ラインを自動化にすることにより、少人数での生産活動に切り替えていくのです。
僕の今の現場は、本当にアナログもいい所です。製品を人員が、目視で全数検査です。すごいでしょう?この時代に、一本ずつ目で見て確認するんです。手間がかかって仕方ないです。そして、2時間に一回の製品の寸法や比重の検査をするのです。
ラインを稼動時の設備や原料の自動記録は、設備が古すぎるためにできません。なので、あの日、あの時の稼働状況を振り返るとなると、帳票類を振り返るぐらいでしかさかのぼることは、できません。
一年前のあの稼動を振り返れってなると、倉庫に行って、大量の資料をひっくり返し、一枚づつ確認します。半年の不良集計を品種別ですることは、紙を一枚づつ見て確認する以外、できません。
時代は、21世紀です。僕は、こんなアナログな作業を6年ほどやっています。このアナログな作業もようやく終わりを迎えようとしています。そうです。設備の自動化をすることになったのです。
机上の空論でのモノづくり
 設備を自動化にするながれになったのは、設備の老朽化もありますが、多くは、建屋の老朽化(耐震強度不足)です。この一件により新たな建屋を建てて、そこでの製造活動が始まります。
設備を自動化にするながれになったのは、設備の老朽化もありますが、多くは、建屋の老朽化(耐震強度不足)です。この一件により新たな建屋を建てて、そこでの製造活動が始まります。
また、工程の短縮化をするとのことで、新たな製造ラインができるのです。以前あったラインを1つ廃棄して、新ラインを作ります。以前からあった製造ラインも移設されるものもあります。
そこで問題発生です。今回の新ラインのライン設計についてなのですが、製造としての意見は、入っていません。製造をしないものだけで、ラインを作成しています。この状況のヤバさが、わかりますか?
直感で、わかる方もいると思いますが、そこで作業をしたことない人の考える設備って、はたして、今までの製造ラインを進化することは、できると思いますか?僕自身は、厳しいと思います。
ラインの立ち上げで、こけるのは、目に見えています。よく僕の会社は、トヨタ自動車のモノづくりを見本に学ぶことを推奨しています。トヨタ自動車といえば日本のモノづくりの最先端をいっています。
トヨタの考えとしては、モノづくりで新たな設備を作るときは、ベテランの手作業を機械化することをします。誰かが使えない設備は、ダメな設備とします。このことを考えると、現場で、物作りをしない人が考えた設備が並びます。
ダメな設備が並ぶことが予想されます。机上の空論で、モノづくりをするんですよ。僕は、これから。多分ですが、中途半端な立ち上げ状態で製造移管されると思っています。なぜそうなるか?
工程優先の悪循環
 製造工程は、待った無しに入ってくるので、いつも通り工程優先になることが目に見えているからです。僕の会社は、どんな状況であれ工程優先です。会社が推奨するトヨタ自動車の考えは、トラブルの原因追求は、徹底的に行い、恒久対策をたててそのトラブルが、今後絶対起こらないようにするそうです。
製造工程は、待った無しに入ってくるので、いつも通り工程優先になることが目に見えているからです。僕の会社は、どんな状況であれ工程優先です。会社が推奨するトヨタ自動車の考えは、トラブルの原因追求は、徹底的に行い、恒久対策をたててそのトラブルが、今後絶対起こらないようにするそうです。
僕の会社は、原因もわからず、とりあえず動けば稼動します。『原因は?』となるとわかっていないので、2度、3度同じトラブルが起こります。これが、工程優先の悪循環です。この工程の悪循環が、常習化している現場なので、今後の展開が見えるのです。
上司が、納得いくまで何度も稼動をさせられて、突発トラブルで稼動ラインを何度もとめさせられるので、動かせと指示を受けた交替勤務の人間は、たまったもんではありません。2時災害、3時災害が起こらないように気を張って稼動をしているので、気疲れが、半端ないです。
そんなことが、日常茶飯事なので、工程優先の会社だというのです。こういった現場なので、現場の作業者は、安全優先とは、建前の工程優先の会社だというのです。大きな怪我になってないだけマシなだけです。
会社では、安全優先とか大きな声で言っていますが、全てパフォーマンスだと思っていますし、怪我の多い現場です。こんな状況でいいのでしょうか?こんな状態で、安定した製造と製品供給できると思いますか?
僕の会社のような工程優先の会社は、多いと思います。こういった工程優先の会社が、起こした不祥事は、最近では、色々とあります。製品の品質が悪い製品を世の中に送り出している企業が、次々にニュースになっています。
そのうち僕の所属する会社も出るように思えて仕方がありません。こういった状況下にいる僕は、日々の生産活動で、色々と考えることがあります。
未来の日本のモノづくり
 僕が、考えるのは、今後のモノづくりのことです。世間では、今後のモノづくりは、オートメイションになると言われています。噂のAIに変わると言われています。そうなると人間は、不要になりますよね。
僕が、考えるのは、今後のモノづくりのことです。世間では、今後のモノづくりは、オートメイションになると言われています。噂のAIに変わると言われています。そうなると人間は、不要になりますよね。
後々は、こういって形になっていくとも思いますが、今の現状は、まだまだ人間の手が必要です。日本の製造業会は、労働人口の減少を作業工程の改善によって補ってきました。
例えば、5人でやっていた作業を3人で、同じ時間で出来るように作業のやり方を工夫してやってきましたが、そういった作業工程の改善にも限界が来ています。しかし、現場の上層部は、まだ作業工程の改善で乗り越えられると思っています。
では、なぜこういった上層部と現場の人間との間に仕事の捉え方に違いが出てくるのでしょうか?
それは、製造量を追いかける人と製造量を生み出す人の違いです。一日、1ヶ月にどれだけ製造さすかと考える人間と、一日、1ヶ月にどれだけ作業をさせられる人間とに別れるからです。
一日のどれだけ製造させるかと考える上層部が、現場の作業員のことを考えて工程を考えるかで、全てが変わります。現場で製造する人間は、多少の余裕が欲しいです。人員、時間の余裕がないとトラブルが起こります。
怪我や設備のトラブル、不良品の流出などがおこります。また、検査員でない人間が、検査を行った企業などもニュースになっていますよね。あれも人員不足の結果だと僕は、思っています。
また、上層部は、現場の状況を考えずに仕事量を増やします。これによって残業時間が膨れ上がります。製造で首の回らないのに、まだ仕事を増やします。現場の作業員は、こなさないといけないので、残業で、その仕事量をカバーします。
上層部は、数しか追いかけてないので、現場の作業員は、どんな状況にあろうと関係ありません。現場の作業員は、ボルトナットと一緒です。ダメなら変えればいいと考えです。しかし、今は、少子化も手伝って、日本の労働人員は、減っています。
それも大幅に減っています。もう少し、現場の作業員のことを考えた生産活動をしていくべきではないでしょうか?これからは、変えるボルトナットは、ありません。使えない人間を集めてきて、人数がいるからとベテラン勢の生産量を作らすのもどうでしょうか?
上司に相談すれば、我慢してやらないといけないと説得しようとします。これが、今の製造業界の現状です。やばいでしょ?
日本人は、働きアリ。こういった昔の良き日本みたいな考えを廃し、時代にあった製造業界を構築していくべきだと僕は、思います。時代の流れと共に製造業界は、これから大きく変わっていくと期待をしています。
そのかわりゆく製造業界で、生き残っていくためには、どうするべきか?次回は、このテーマについて書いていきたいと思います。
本日も最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございます。
次回もよろしくお願いします。