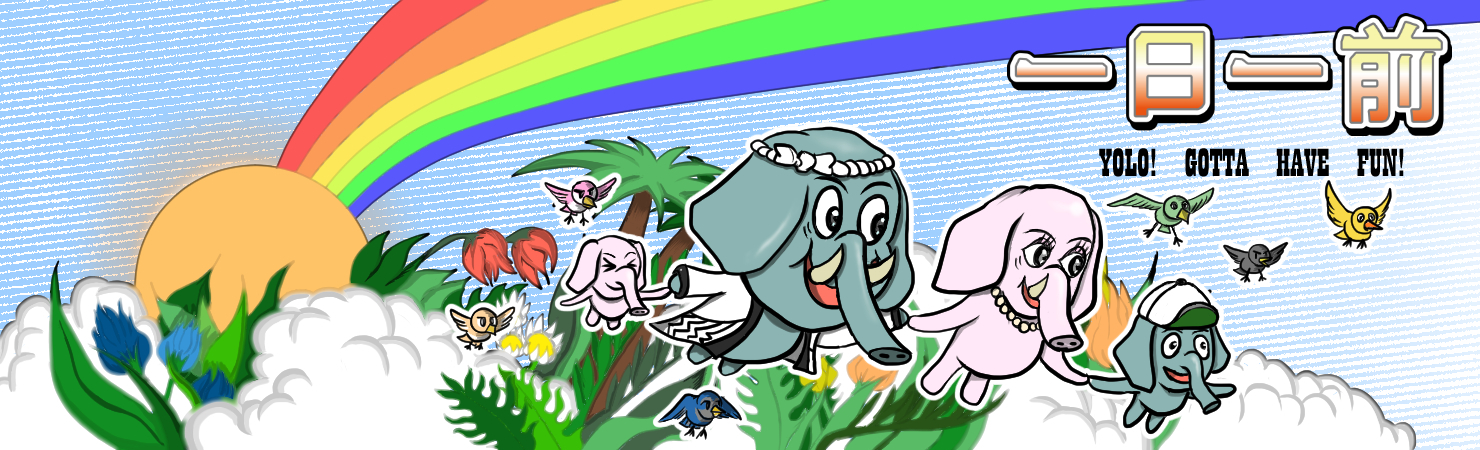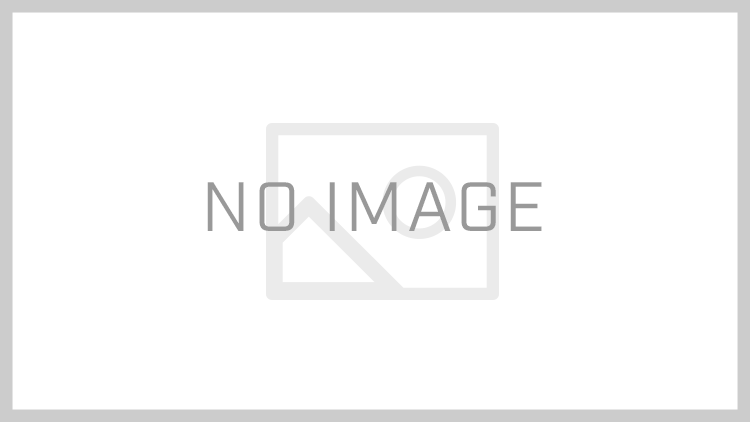新人教育って、本当に大変ですよね。まずは、自分がどれだけ仕事のことを理解できているかが試されます。そして、教える時になぜそれをするのかを明確に伝えなければいけません。
伝えるといっても、相手が理解して、腑に落ちていないと意味がありません。現在、僕は、訳があって交代勤務から日勤勤務へと変わり、新人教育に力を入れているのですが、苦悩の日々を過ごしています。
しかし、充実しているんですね。本当に楽しいです。新人なので、現場作業を教えるだけではなく、社会人として、今後の役に立つ考え方なども教えています。新人の役に少しは、立って入ればいいのですが。
新人教育の過去と現代
大好きな読者で学んだことなのですが、今の新人教育と過去の新人教育の違いって分かりますか?時代背景が大きく関わっているのですが、労働人口の減少に伴い、一人前になるまでの時間が短いということです。
過去は、職場に人が多くいましたので、10年で一人前になればいいとされていました。一人の新入社員に、多くの先輩上司が関わっていました。しかし、現在は、よく聞く『人手不足』ってやつですよ。
そのために3年で一人前になれっていうことが世間の平均的な声だそうです。そして現場は、仕事量が多く、新人教育に時間を割けないといった状況です。なので新入社員の離職率が高いです。また、部下に無関心という管理職も多いと言われています。
このような状況で、『人手不足』といっている職場が多いのです。教育に時間を割きたくない企業は、即戦力を求めます。よく、転職サイトのCMを見ると『即戦力』っていっています。
そんな状況では、数年後の日本の社会は、どうなってしまうのでしょうか?すごい心配ですよね。さて、現代の新人教育について、管理職の方達は、どのように考えているのでしょうか?
教育スケジュールが組めない
現代の管理職の人たちって、教育スケジュールを組むことができないんですね。これは、僕自身も現場で実感しています。それは、なぜか?
管理職の人達って、自分で力でやってきた経緯があるので、人に教えることが苦手なんですよね。また、人を育てたことのない管理職の人も多いのが現代です。まず、新入社員にコミュニケーションをあまりとりません。
あなたの現場を見ていてどうでしょうか?新入社員と管理職の人たちがコミュニケーションをとっている光景をよく目にしますか?よく目にする職場は、人がよく育っていると思います。
僕の現場では、新入社員の状況などを周囲の先輩社員に聞いたり、新入社員の本人に仕事をしていて感じることなどをリスニングしたりしません。仕事内容も誰かの手伝いで、雑用のような仕事しかさせません。
安全を考慮してと見ている作業も多いです。これでは、自分は必要とされていないと感じますよね。人間って、そう感じるとヤル気がなくなっていきます。その現状からいきなり交代勤務に放り込まれ、急に責任感を押し付けられるので、失敗を許されません。
そんな状況下で、あなたなら僕の職場で仕事をしたいと思いますか?今の現状は、1年間は、交代勤務をさせないとの上司からのお達しのため、交代勤務になることは、ないそうです。
僕が見て、ただの新入社員の離職を延命しているだけとしか感じません。新入社員の状況も確認せず、指示も出さないと見ると管理職の方も勝手に育つと思っているようにしか思えません。
社内メールという便利なものがあるのですが、大事なことをその社内メール一本で終わらす上司もどうかと思います。それでは、人間関係も構築できませんし、不信感しか生まれません。 そこで、自分が育てるんだとの意気込みで教育スケジュールを組むことにしました。
人材を育てる
日勤勤務になった当初の僕は、怪我をしていた為にまともに作業をすることが出来ませんでした。まず、自分にできることは、何かと考え、3人の新入社員と2年目の社員を育成することにしました。
そのことを上司に申し出て、まずは、4人の現状について紙に書いてもらいました。 30分ほどですが、予想をしていたような意見が書かれていました。やはり、現状の雑用のような仕事に違和感を感じ、自分たちの中途半端な立ち位置に困っていました。
そこで、週替わりで4人に教育者をつけることにしました。一人は、交代勤務の教育を受け、もう一人は、製造原料の補充作業の教育を受け、2人は、僕が現場の設備の保全業務や改善業務を教育することにしました。
目標としては、3つあります。
- 交代業務の基本である作業を一人ですることができるようになること。
- 設備の構造を理解し、楽に仕事をするために設備をどう改造するといいか考える力をつけること。
- 製造製品の原料を理解し、製造工程を理解すること。
交代作業員は、ギリギリの人数で作業をしているため、作業をカバーできる人員が必要です。欠員補填などもできるようにとの想い出、交代作業者の人にお願いをして教育をしてもらっています。
設備の保全作業は、ドリルで穴を開けたり、ネジを切ったりなどの作業です。この作業は、設備を理解していないといけませんし、一緒に作業をしないと身につきません。
ベテランの作業員に裏方となる原料の補充作業を教育してもらっています。そこで、どのようにして製品ができるのかなども教えてもらっています。
そして、全ての作業で失敗を恐れないようにと念を押して言っています。慣れない作業をして失敗することは、当たり前です。これを怖がっては、成長はありません。失敗の責任は、全部僕が持つと言っています。
事細かに全ての教育者と連携をとって、新入社員の状況を聞いて、新入社員と2年目の社員にもコミュニケーションを取るようにしています。9月1日から始めたので、1ヶ月間、今の教育体制でどうだったかをリスニングしようと思っています。
この教育をして、1ヶ月ですが僕自身に気づきがありました。
期待と信頼
それは、人を教育するってことは、相手を信頼しないとこちらの教育態度も荒くなってしまい、教育者も教育される側も成長しないということです。
2年目の社員を教育していた時に気づいたのですが、1年間、交代勤務をしていたのだから基本的なことは、出来るだろうとこちらの勝手な思惑もありますが、期待をしていました。
しかし、予想以上に基本的な作業ができません。期待をしていたので、どうすればいいものかと悩みましたし、教えてる自分の口調が荒くなっていることに気がつきました。
そこで、なぜこうなっているのかと自問自答をしました。ここで、期待とは、何かと考え調べました。
期待・・・・・自分の思い通りに動いて欲しい、相手を支配するとか操作するといった意識
このことが分かって、どのような想いで教育するべきか考えた時に、相手を信頼することだと気付きました。信頼をすることで、彼に教育しても出来ない理由があると思うようになったんです。
どのようにしたら伝わるのかと考えるようになり、色々と工夫をしながら教育することにしました。その結果、まだ少しですが仕事を任せられるようになってきました。
- 時代背景により、新入社員は、3年で一人前になれという風潮であること
- 人を育てられる管理職が少ないこと
- 部下を教育するときは、期待するのではなく、信頼すること
人を育てるって、学ぶことが多いですね。時代背景により、自分が教育を受けていた時代の教育の仕方とは、変わっていますが現代には、現代の教育方法があるので、それにあった教育をするべきだと思います。
あなたの職場でも新入社員を期待するのではなく、信頼をして、新入社員もあなたも良き環境で成長しませんか?良かったら、職場で実践して見てください。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。
次回もよろしくお願いします。